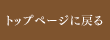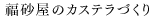■「岬の教会の南蛮屏風」(逸翁美術館蔵)
(福砂屋カステラ読本より)
日本にカステラが伝えられたのは16世紀中期のこと。南蛮貿易の港として賑わう長崎の町で、パンと共にカステラも焼かれるようになります。のちにカステラは、その製法に変化をつけながら、南蛮菓子を越えて徐々に日本化し、その栄養価の高さから、医学に携わる者たちを中心に、全国に広まっていきました。

■「職人尽くし図」御菓子所 川原慶賀(かわはら けいが)筆(オランダ/ライデン国立民俗学博物館蔵)
(福砂屋カステラ読本より)
日本に伝わったカステラの最初の製法としては、材料は、小麦粉、砂糖、卵の三種類。材料の配合は、すべて同量です。それらを混ぜ合わせて、蒸し焼き鍋(形は長方形、丸形の二種類)に入れ、蓋をして火で上下から焼くというものでした。
その後江戸時代初期から時代の変遷に従って、素材の配合や甘味料などが徐々に変化し、カステラは、製法共々日本人の味覚に合うように各地で工夫されてまいりました。
甘味料においては、砂糖と共に日本人の嗜好に合う水飴が使われるようになりました。
上火、下火が調節できる和製オーブンとも言える「引き釜」を使いこなすなど、製法にも改良が加えられ、しっとりとした日本独特のカステラができあがったのです。
カステラという名前は、河北温山の記した『原城紀事』や、『長崎虫眼鏡』、『長崎夜話草』、『諸国板行帖』など様々な文献に登場します。
カステラは文献によってさまざまに表記されていますが、これは日本人がポルトガル人からカステラを表す語を聞いたときに、人によって聞き取り方が違ったということをあらわしているのではないかともされています。